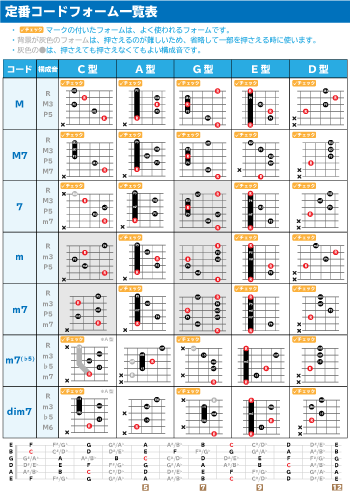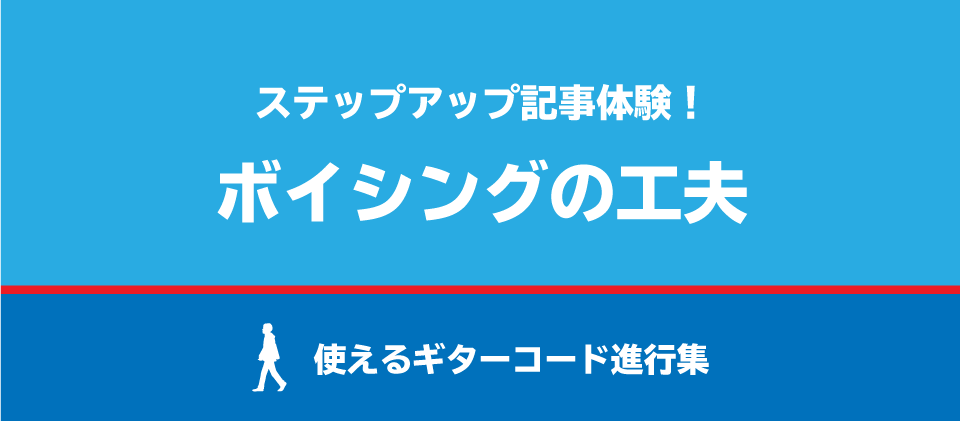
使えるギターコード進行集のステップアップ体験記事にようこそ!
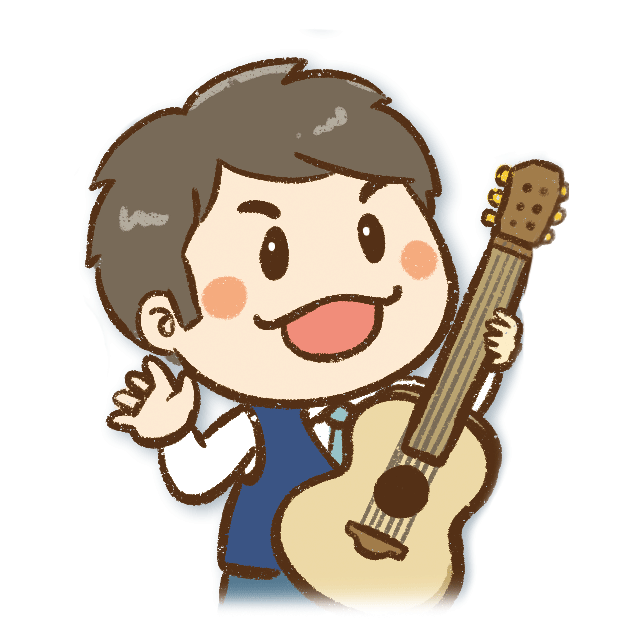
この記事では、ステップアップ記事の3記事目
「Step03.ボイシングの工夫」をご体験頂けます!
ボイシングの基本
ボイシング=ギターフォーム
「コードは構成音だけを示し、重ね方は問わない」という原則があります。そのため、音の重ね順を変えること自体は全く問題ありません。
音の重ね方のことを、ボイシングと呼びます。
ギターにおいては、ボイシング=ギターフォームと考えてもらって構いません。フォームを変えると、ボイシングが変わります。
例えば、CM7(9)の場合を見てみましょう。
この例をとっても、フォーム(音の並び方)によって、全く音の印象が違うことが分かると思います。
どの場面で、どのフォーム・ボイシングを選ぶのかが、作曲・編曲においてはとても重要です。
構成音は3種類に分けられる
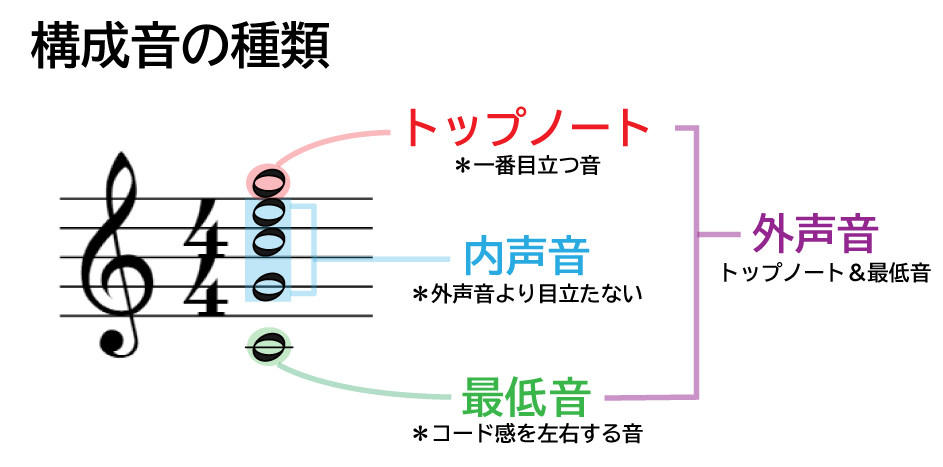
聴覚上、影響度が高い順から、トップノート>最低音>内声音です。
フォームを迷ったら、まずはトップノートの音から先に決め、逆算してフォームを選ぶのがおすすめです。
スムーズなボイスリーディング
ボイスリーディングとは、コードが変わる時の構成音の動きのことを言います。
例)不自然なボイスリーディング
脈絡なくフォームを選択すると、不自然に聞こえます。
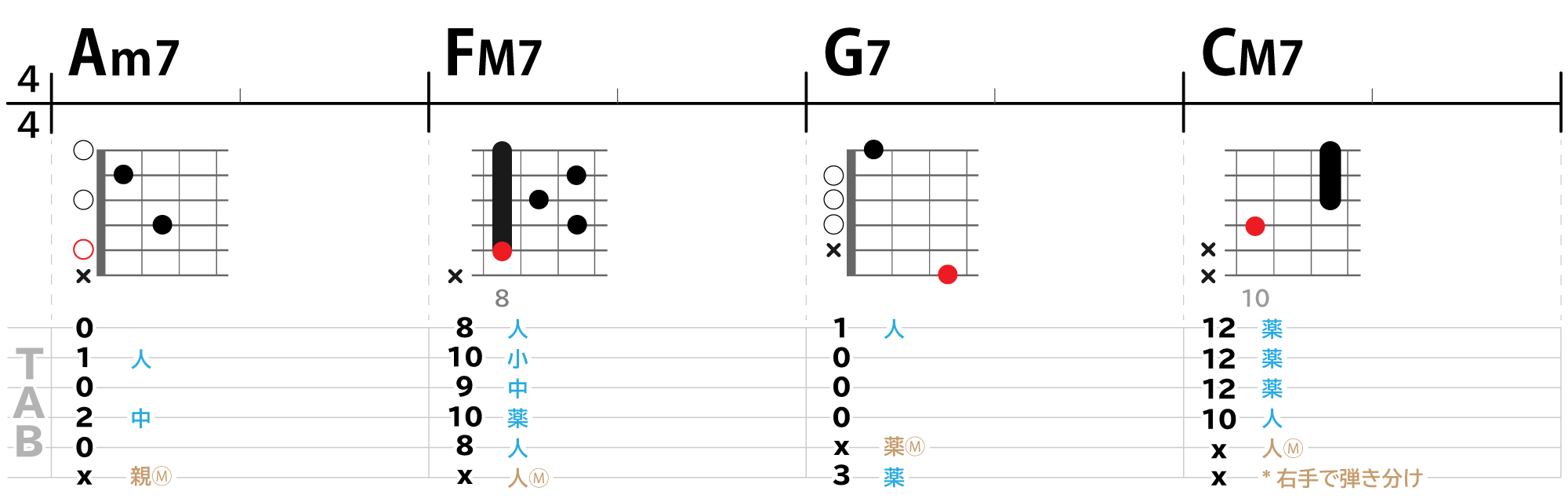
こんな風に弾く人はいないと思いますが、指板を行ったり来たりで演奏しづらい上に、音の流れも不自然ですよね。
例)自然なボイスリーディング
ギターにおける、スムーズなボイスリーディングの基本は、近いポジションのフォームを選ぶことです。
先程の不自然な進行を、7~10フレットの間のフォームに直して、自然にしてみます。
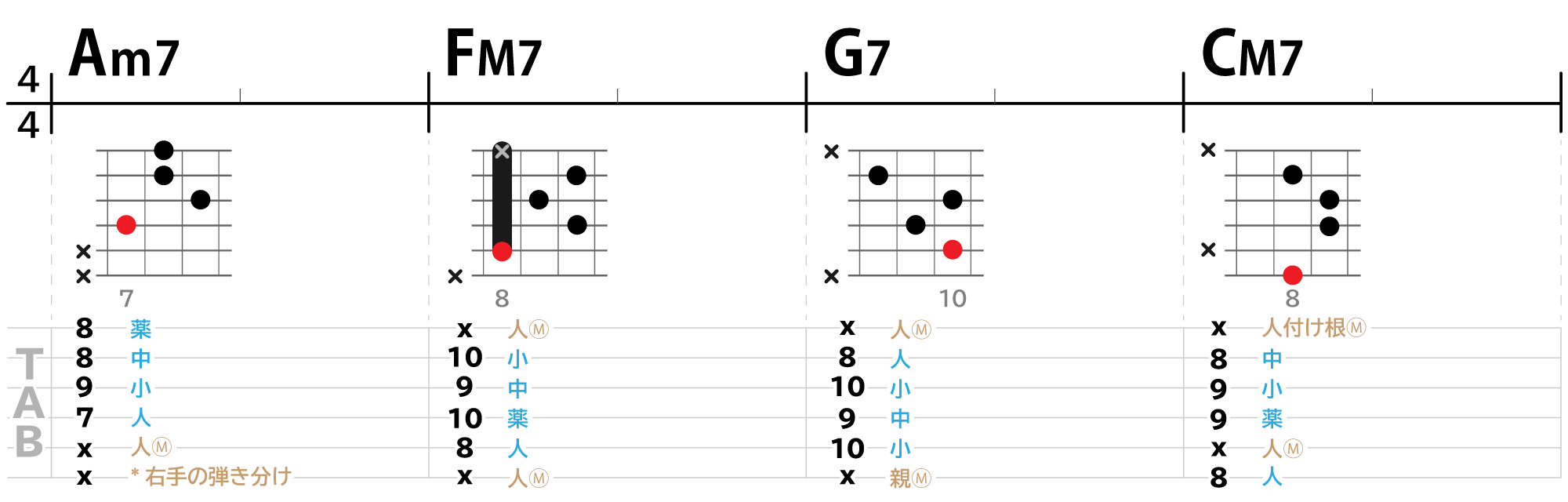
とても自然ですよね。
次のフォームは、隣のポジションのフォームを選択することで、トップノートを上行する流れを作っています。
1・2小節は7~10フレットで、3・4小節は10~12フレット。
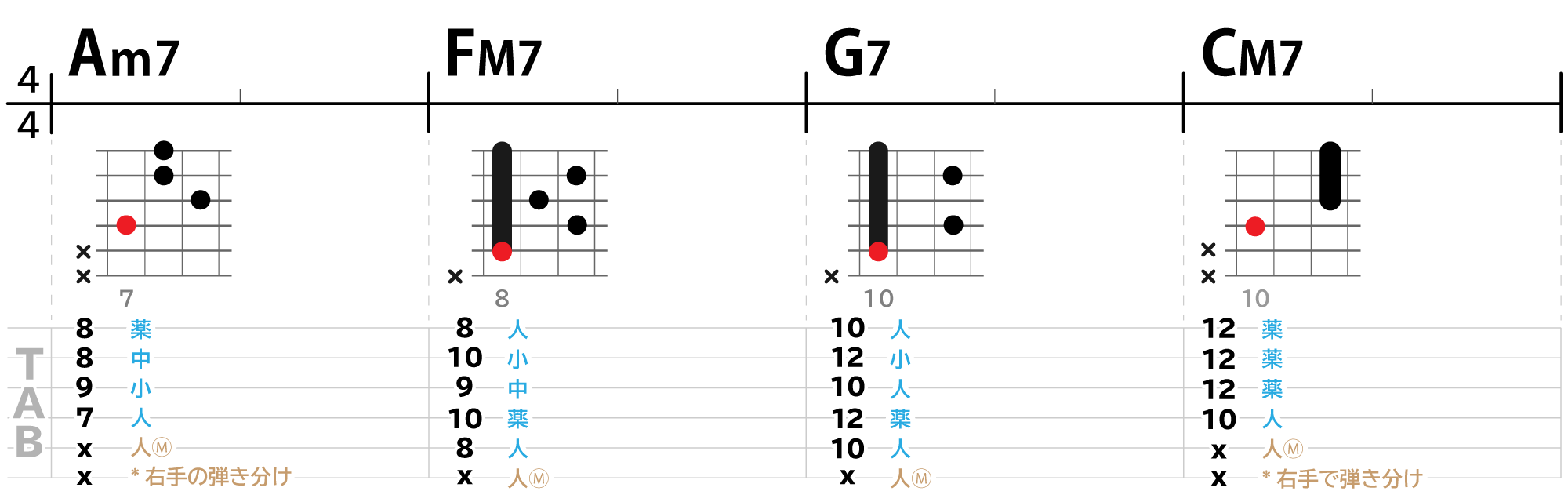
このように自然なボイスリーディングの鍵は、同じ、または隣のポジションのフォームを選択することです。
ポジションを変えないフォームの練習法
下記の譜面では、最後の小節以外、7~10フレットのポジションを使用しています。
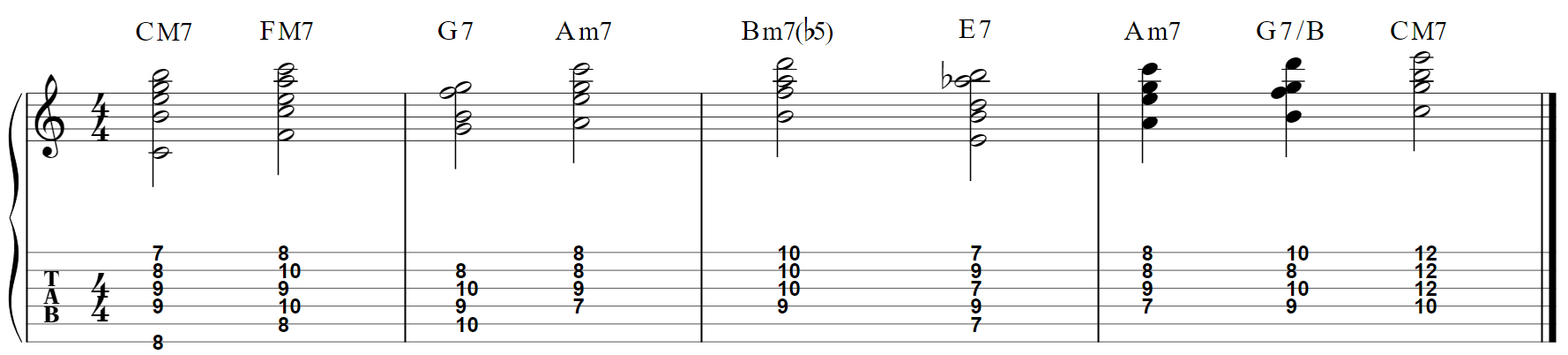
- 右手のパターンは自由です。
- 最初はテンポを落としても構いません。
- 慣れてきたら、テンポを一定にして演奏します。
苦手なキーやコードを組み込んだ練習メニューを、自分で組んで練習すると効果的です。
定番フォーム一覧表の活用
ポジションに応じたフォームは、定番フォーム一覧表を活用すると、探しやすくなります。
ここからダウンロード! – *実際のページではダウンロード可能。
- 【参考】定番フォーム一覧表の使い方の例
-
今回は5弦ルートのE♭7を作ります。
表の下部には、指板音名表が掲載されています。ここからE♭を探します。
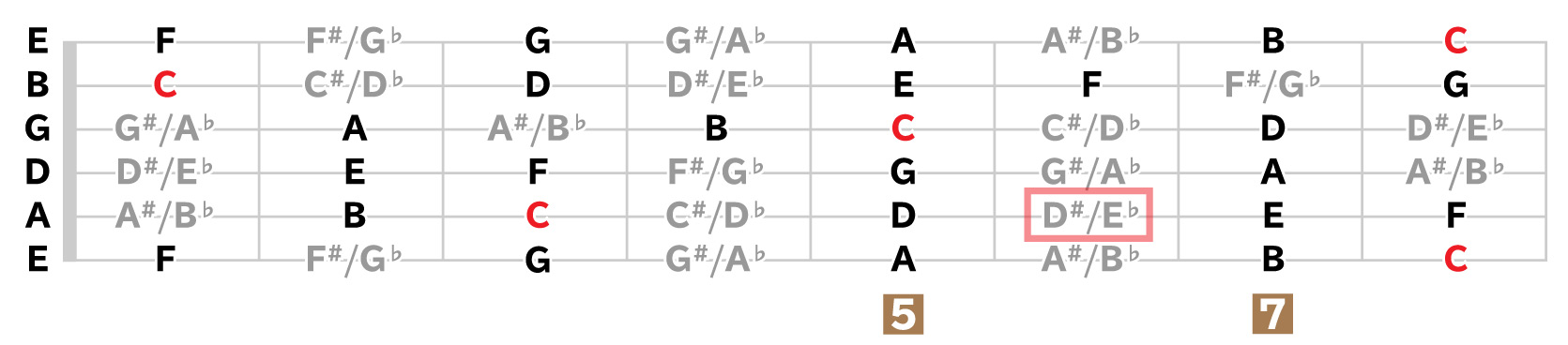
5弦6フレットにE♭がありますね。
そして、表の7の段を見てみます。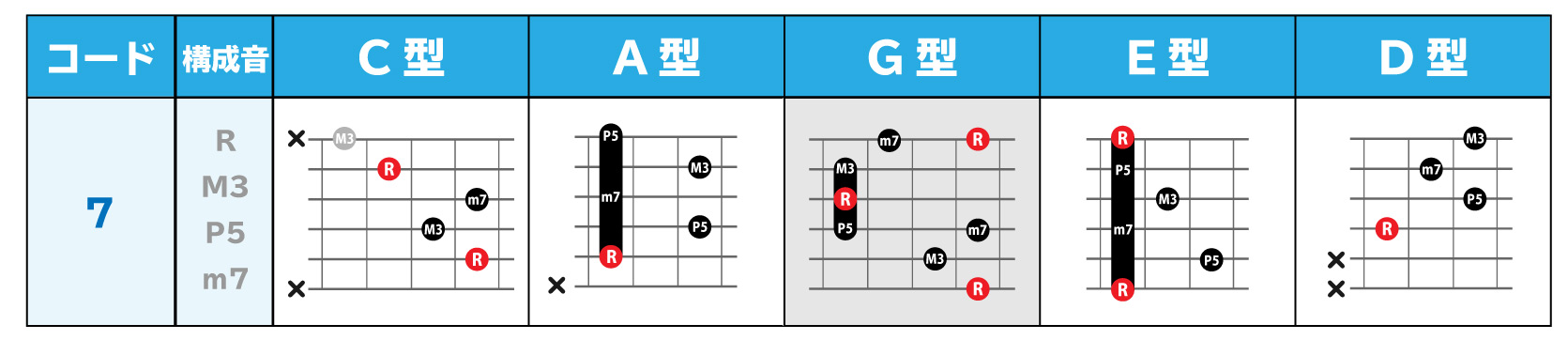
5弦ルートはC型・A型ですね。つまり、E♭7の5弦フォームは次の2つです!
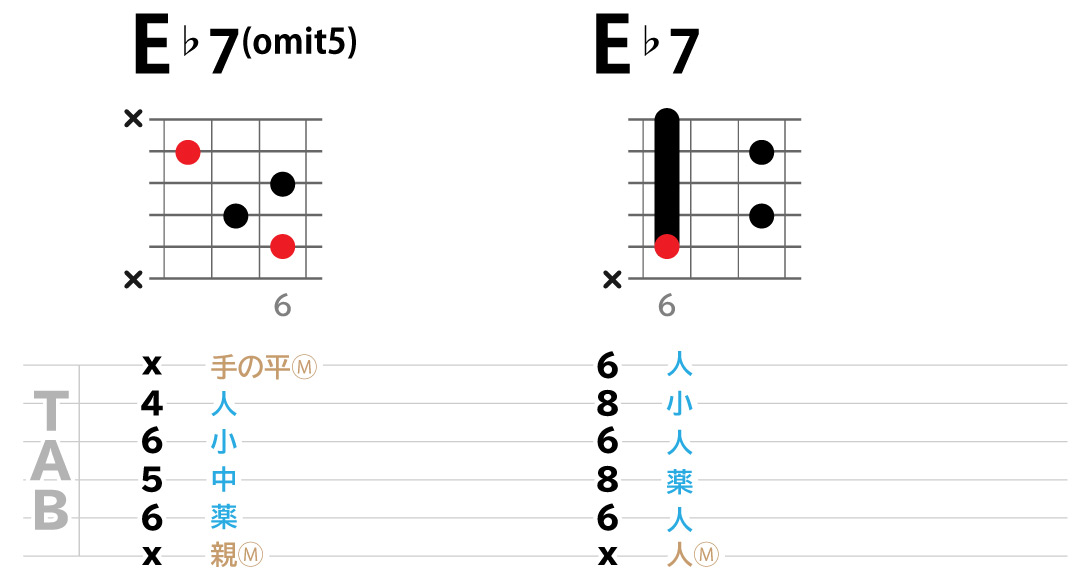
別フォームを選べるメリット
同じコードでも別フォームを選択できると、色々なメリットがあります。
ここでは、下記3つのメリットを、実例を交えてご紹介します。
- スムーズなボイスリーディング
- 動きのある演奏が可能に
- 濁って聞こえるコードの改善
スムーズなボイスリーディングを作れる!
Key=E(C#m)のダイアトニックコードである、C#m7。定番フォームは、x46454 というバレーコードです。
そのため、トニックのEの定番フォーム(022100)とは、ポジションが離れているのが気になる所です。
そこで、次の進行の1小節目では、違うC#m7のフォームで弾いています。
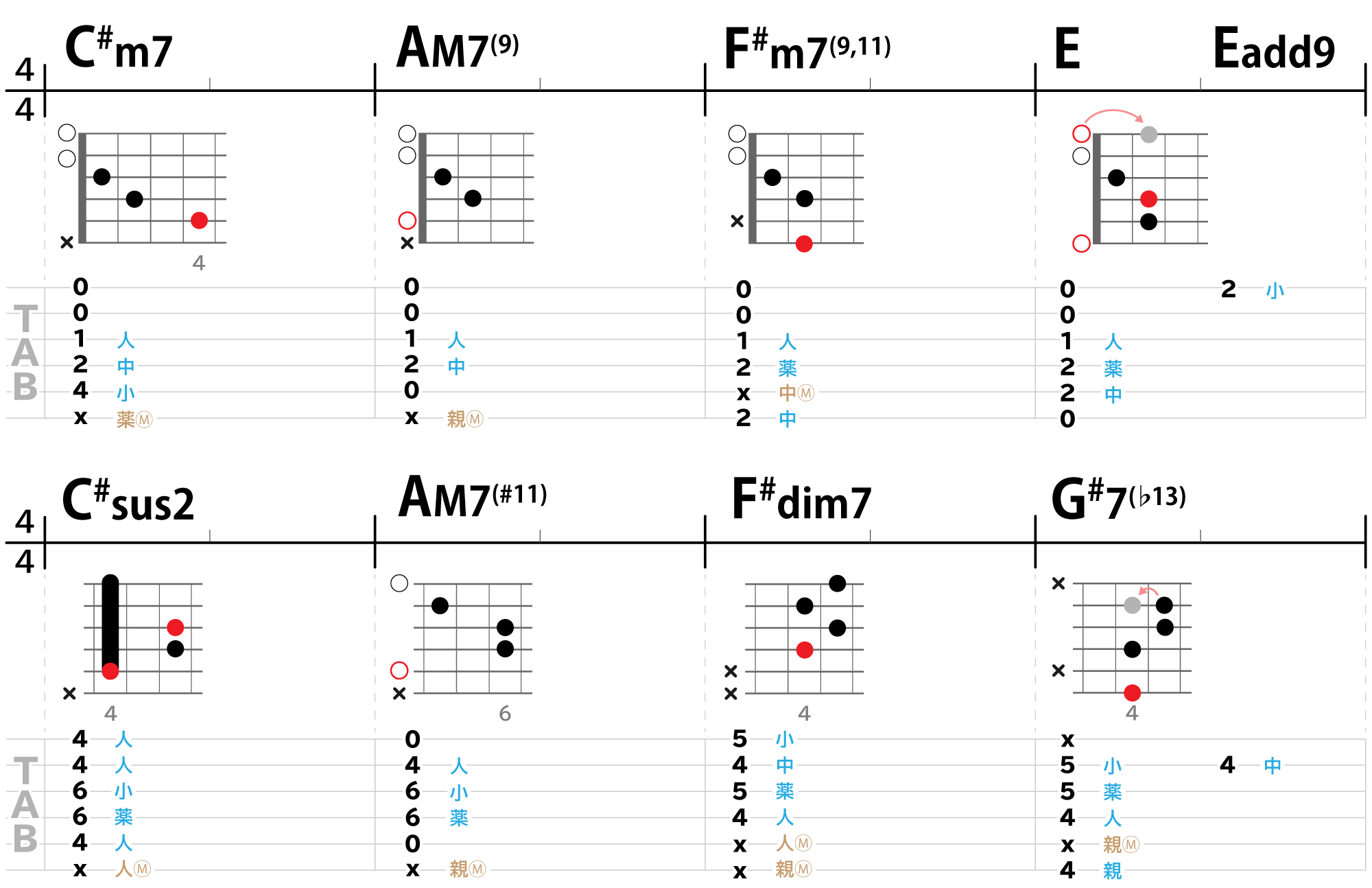
これによって、1~4小節で、1~3弦の構成音が維持された進行が実現しました。こうした構成音の維持をペダルポイントと言います。スムーズなボイスリーディングの最たるものですね。
実際にどのようにC#m7の別フォームを導き出したかについては、No.35✓大事なポイントで詳細に解説しました。
動きのある演奏ができるようになる!
同じコードを違うフォームで押さえられるようになると、動きのある演奏がしやすくなります。
【基本】別フォームを選ぶ
次の進行の5・6小節を見てみましょう。
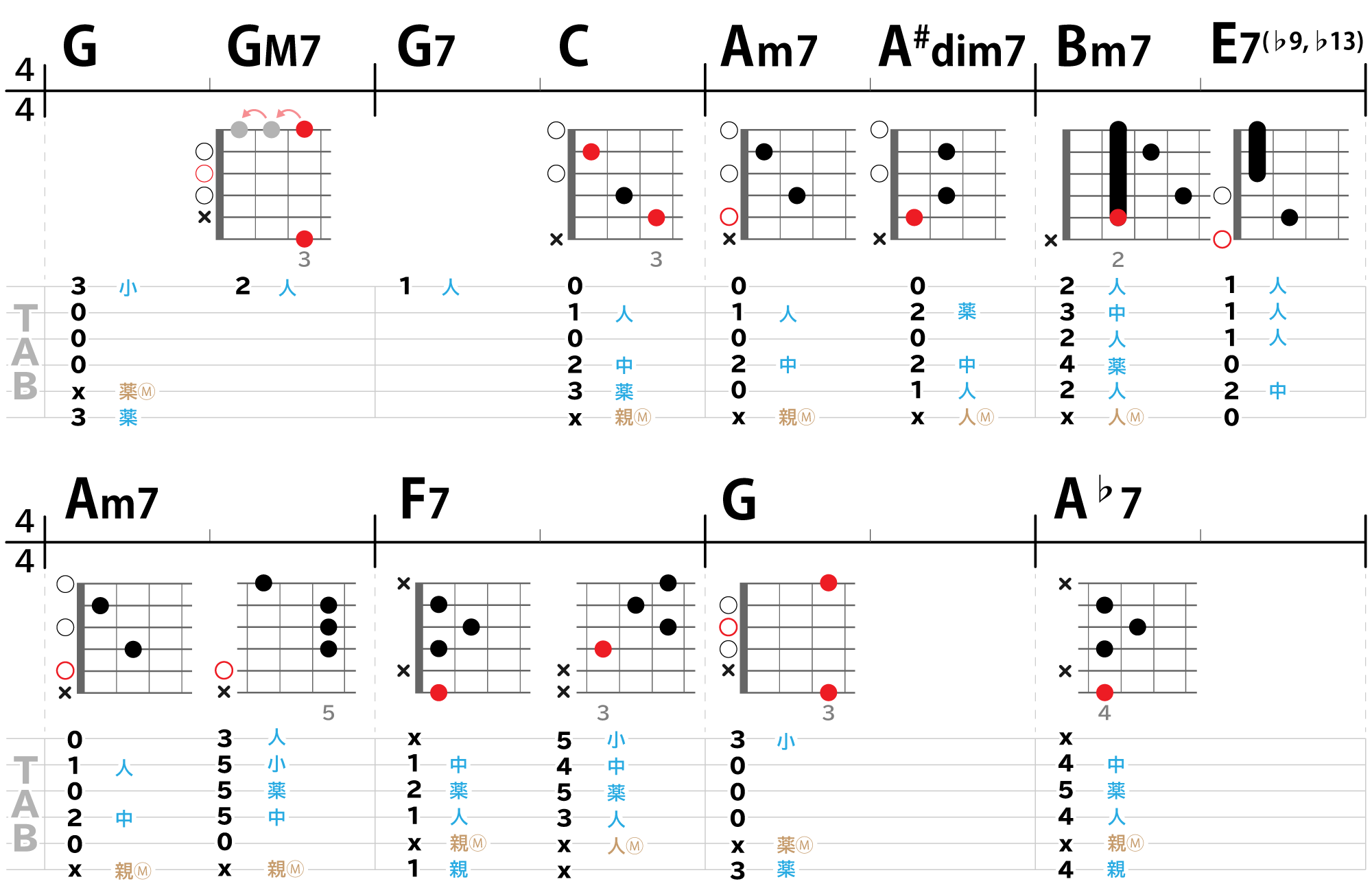
Am7とF7を、別フォームに変化させることによって、同じコードなのに動きが出ているのが分かりますよね。
【応用】別フォームにテンションを加える
次の進行の1・2小節目では、別フォームに、更にテンションを加えて、変化させた例です。
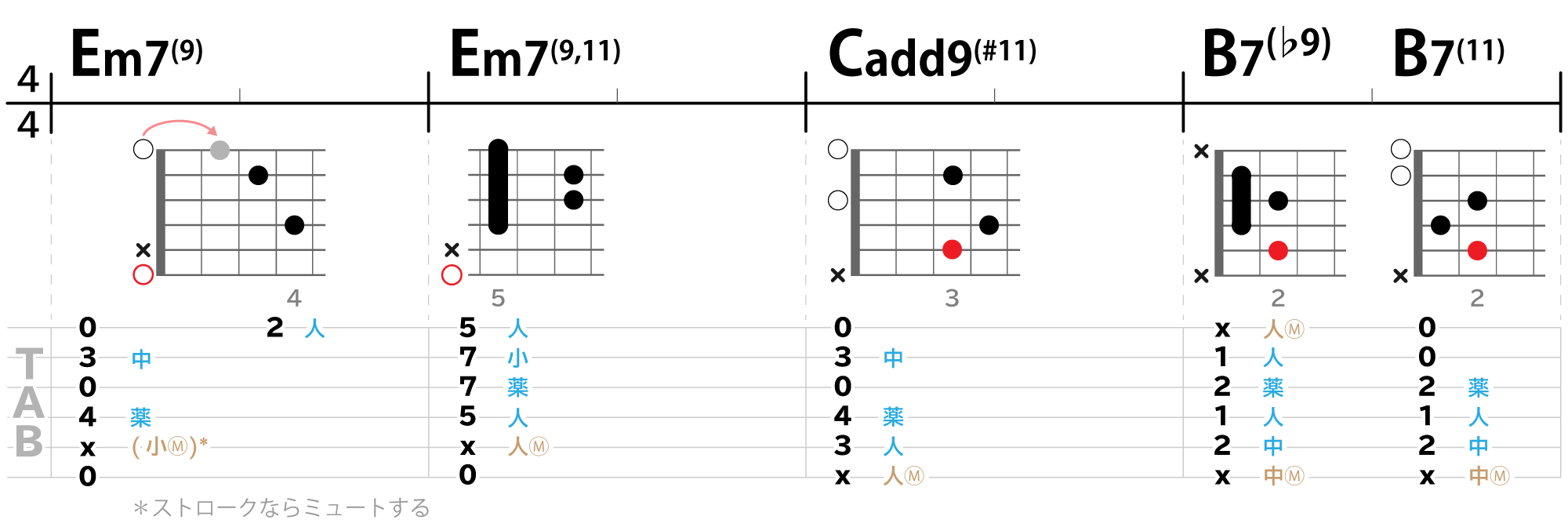
2小節目のEm7(9,11)の元になったのは、Em7(9):075770 というフォームです。
このコードを元に、トップノートを高めるために、アヴェイラブルテンション11のA(ラ):1弦5フレット目を加え、上記のようなフォームになっています。
別フォームを選ぶことで、動きのある演奏になっていますよね。
濁って聞こえるコードの改善!
和音を重ねる際に、低い音域で重ねると、音が濁って聞こえます。その濁るか濁らないかの境界を、ローインターバルリミットと呼びます。
楽器の音色によっても、ローインターバルリミットは変わってきます。
例えば私には、Gの定番フォーム(320003)は、5・6弦が濁って聞こえます。そのため5弦をミュートして、3×0003と押さえることがほとんどです。このような省略もボイシングテクニックの一つですね!
また、EM7の定番フォーム(021100)の4・6弦も濁って聞こえます。そのため生み出した、新しい押さえ方が次の進行の1小節目です。
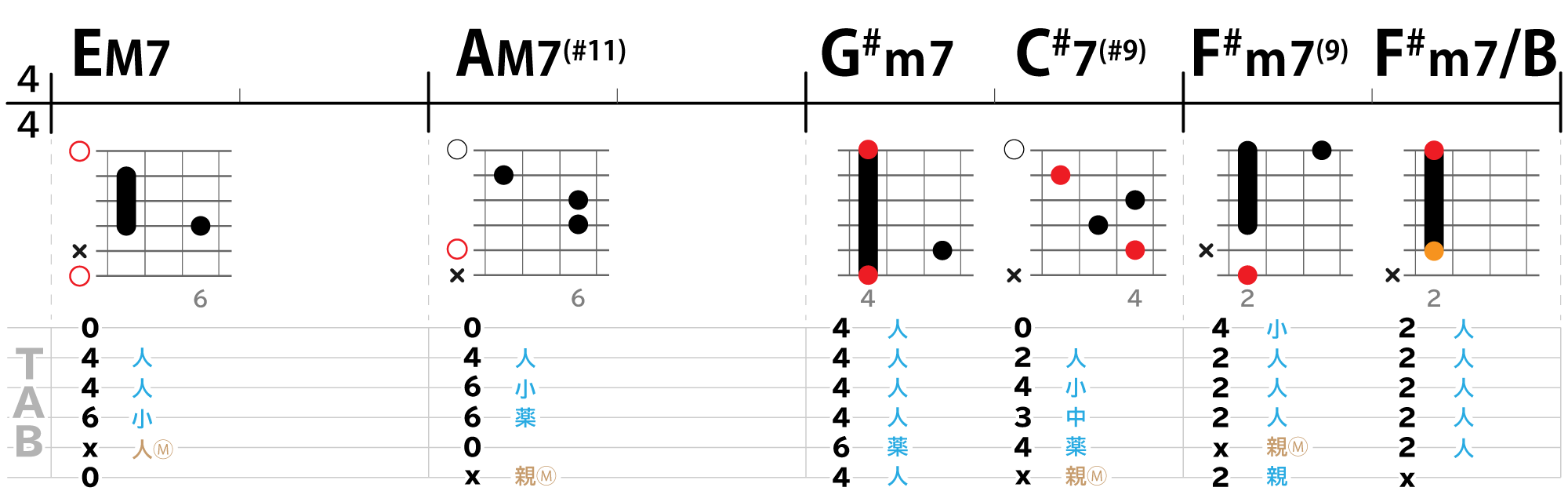
いかがでしょうか。低音の濁りがなく、とても美しい響きになっているのが分かりますよね。
このEM7フォーム(0x6440)の導き方についても、No.59✓大事なポイントでご覧頂けます。
不思議な響きを生むボイシング
不思議で効果的な響きを作る、特別なボイシングテクニックをご紹介します。
- 長二度音程の神秘的な響き
- 短二度の美しく不穏な響き
- 弦の高低差が逆になるボイシング
本項目は、購入後ご覧いただけます。
以上、使えるギターコード進行集「Step.03ボイシングの工夫」です。途中までですが、かなり濃密な内容だと思います。
ステップアップ記事で、コードテクニックを網羅しましょう!
ぜひ使えるギターコード進行集のご購入を検討してみて下さい。